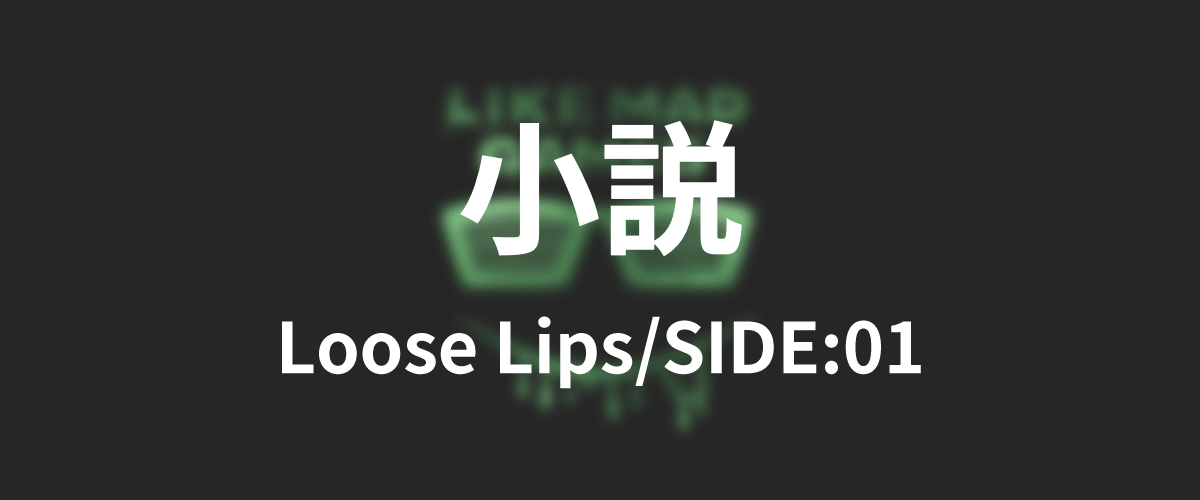Loose Lipsシリーズについて
Loose Lipsの今後の展開について
ノベルゲームで読む
ブラウザで読む
『地獄から始まって地獄で終わる』終わらせる為の物語。
元刑事のカサイとシリアルキラーのセドリック。
二人は司法省からの依頼で未解決事件へと取り組むのだが――――
Loose Lips(SIDE:foggy)第一話
【できもしない事を口に出す意味は、ただの自己暗示だ】
刑務官が俺のことをじっと見ている。ガムを噛む音、目つき、その息遣い。全てが不快だ。考えている事はどうせ碌でもない事だろう。昨晩のレッドタートルズの試合結果や、今夜の試合を観ながら飲むビールについて。この辺りの中年男が考えている事と言えば、普通はそれくらいのものだ。だけど、なんにでも例外はある。唯一それはこの俺を――――トール・カサイを見る時だ。その時だけは別の事柄が頭に浮かぶ筈だ。それを俺はできるだけ考えないように、聞こえない声に耳を傾けないように努めた。そうして黙ったままスーツの上着のポケットの中の物をスチール製のトレイに乗せた。
「あとで連れて行く 面会室で待つように」
俺には『どうぞごゆっくり』と聞こえた。思わず目を細めて聞き返しそうになったが、これも俺の思い込みであると気にする事をやめた。
あれから。あれからずっとだ。セディ――――セドリック・スウィーニーの公判以降、世間の俺を見る目は好奇と悪意に満ちている。時折、理解を示そうと近づいてくる者もいるが、それは上っ面だけだ。どんな人間にも俺の身に起こった出来事を真に理解する事は出来ない。しかし、これにも例外はある。その例外は今入ったばかりの薄暗く光量の少ない電球が照らす面会室へとじきやってくる。
俺は机の上に必要なものを広げて並べた。あとはサンドイッチの紙袋も置いた。これは俺が食べるものじゃない。ヤツに――――もうじきやってくる例外に頼まれたものだ。報酬とでも言うのだろうか。だが、ヤツにとっての本当の報酬は…あまり言葉にしたくはないが、この俺自身だった。
狭い廊下に響く足音。ペタンペタンとスリッパをだらしなく遊ばせるような音が聞こえてきた。それを聞いている俺の右手が意味もなくペンを回し、組んでいる足の先も同時にぶらつく。時間なら腐るほどにある。こんな事は考える気も失せるのだが、俺は社会的な信用を失くし、警察官と言う仕事を辞めた。今はフリーの探偵だ。
以前、世話になったトライモント署のボスに雇われて、どうにか飯は食えてはいるが…そう、時間だけなら腐るほどに、人生が長すぎると感じるほどに持て余している。
「どうぞごゆっくり」
ドアが僅かに開いた向こう――――廊下で誰かがセディに言った。間違いなくはっきりと。その言葉をブロンドヘアのセディが笑顔で聞き届けると、手と足を繋ぐロープを外され、俺の正面の椅子に座った。
「やぁ、Mr.カサイ
今日も見逃してもらえた?」
肩まである長めの髪を揺らして明るい口調で俺に問う。だが、いつだって俺を見るそのデカイ目は湿気を帯び、陰鬱さをまとっている。
「あぁ、クソッタレが今日もレコーダーを見逃してくれたさ。上からの書簡があるからな」
死刑囚との面会など一般人の俺には簡単ではない。だが、それが司法省のお偉方の命令であれば話は別だ。俺が《警察を辞めた※※野郎》であってもレコーダーを持ち込んでの面会が可能だった。
「それで、今日はどんな事件? 誰を捕まえて欲しいの?」
セディの目の色が変わる。途端に輝きを見せるから厄介だ。そしてこの瞬間、毎回俺は殺人犯と二人きりで薄暗い部屋にいる現実を思い知らされる。思わず手元にあるタンブラーの水を飲んだ。
「先に言っておくと、面白くない事件はやる気が起きないから。わかるでしょ? 僕が楽しめるものにしてよ」
いちいちうるさいヤツだ。
「死人が出てる事件に楽しいもクソもないだろう」
「これはどうだ? ふたつき前にブルーチェで起きた10代少女の惨殺事件」
俺はセディに事件記録のフォルダーを渡した。今日持ってきた事件は23件ほどで、連続殺人事件と判明しているものは、たった1件だ。
「面白くない」
セディは俺の渡した記録に少し目を通しただけで、机の上に伏せてしまった。そしてサンドイッチの袋に手を伸ばし、断りもなくかぶりつく。
「これは養父だ。犯人は養父。12歳なのに処女じゃなかったんでしょ? 日頃から虐待を受けてたんだろう。犯人は養父に決まり。次の事件記録を見せてよ」
サンドイッチを頬張りながら、よくもこうベラベラと喋れるものだと感心する。もちろんいい意味では言っていない。俺は仕方がなく次の事件記録をセディに渡した。その瞬間、フォルダーを持つ俺の手にセディのものが重ねられた。冷たくごわついた手のひらの感触が手の甲へ伝わり、何が起きたのかをそこでようやく理解した。
「僕は良いんだよ? 君がもったいぶって最後に重要な事件を見せたって。その分、ここで楽しめるんだから」
そう言ったセディは、俺の手の甲を親指の腹でさすった。その瞬間、口の中に苦味が広がり、いつかの誘導灯の赤いランプが頭にチラつく。俺は勢いよく手を引いた
「何もするな! 黙ってろ! お前は俺らの《道具》に過ぎない事をよく覚えておけ」
セディは軽く顎を引くと、再び湿っぽく陰鬱な目で俺を見つめた。
「僕より優位に立ちたいのは、今の君の社会的地位と関係がありそうだね。でもいいよ。君の心地よさが僕の悦びだから」
何を言っても空気をたたくようなものだ。だから俺は近頃、気にしない事を学んだ。気にすれば嫌でも考えてしまうからだ。
「確かにお前の言う通りだ。早く終わらせよう」
連続殺人事件だと判明している、たった一つの事件記録をセディへと投げた。だが、俺は正直その事件には乗り気ではない。扱う事件はここ西海岸のトライモント周辺が中心にはなっているが…司法省は俺の都合に構うことなく、東海岸だろうが…とにかく場所に関係なく未解決事件を寄越してくる。つまり飛行機を使うような距離の事件だと言うことだ。
「東海岸に行ったことがないんだよね」
その言葉に俺は机を二度ノックした。
「待て、お前には前科がある。前科と言うのは、殺しの話じゃなくて…」
「ガソリンタンクの件?」
「そうだ、それだ。だからお前が塀の外へ出ることは、もう二度とない」
死刑囚の釈放が許されただけでも奇跡だと言うのに、それが二度もあってたまるか。神ですら一度しか蘇らなかったと言うのに。
「だけど、よく考えて。僕一人を塀の外へ出すだけで、連続殺人事件が解決するんだ。捜査組織も予算削減で人手不足なら、尚更…僕を出すべきだと思うけどね」
随分な自信だ。だが今の所、この男が捜査協力した事件は、どれもこれも数ヶ月以内に解決している。捜査組織が何年かかってもホシのあたりすらつけられなかった事件でもだ。
でも、俺は思う。司法省もトライモント警察も良いカードを引あてたと考えているだろうが、この男は殺人鬼だ。いつか絶対に裏切る日が来ると――――――机の上の電話が鳴った。
「はい、カサイです」
「どうも、カサイさん」
「…………あ? 誰だ?」
「刑事のエド・フィッシャーです! いい加減、覚えて下さいよ」
てっきりボスからの電話だと思ったが、まぁいい。俺は用件を尋ねた。
「エドか 何の用だ?」
「実はボスから伝言を頼まれまして…」
エドが話したのは、ちょうど話題に上がっている東海岸の事件についての続報だった。数時間前にまたしても似たような手口で殺害された遺体が発見されたという事だった。
「早急に犯人を捕まえろ…そういうことだな?」
目だけでセディを見ると、声を出さず俺に何かを言っていた。それを読み取ろうと意識を集中したせいで、エドの話を聞き逃してしまった。
「悪い、エド もう一度言ってくれ」
「ですから、セドリック・スウィーニーの釈放申請を提出するので、許可が下りたら、数日分の荷物をまとめて東海岸に行って下さい」
「冗談だろ!? 冗談だと言え!」
思わず怒鳴ったが、エドに言っても仕方がない。俺は額に手を当てると電話を切った。そんな俺をセディはニヤニヤと薄気味悪い顔で見ている。
「飛行機に乗るんだよね?」
「それの何が嬉しい?」
エドの話を聞いていたのか、自分の釈放が決定的であると知ったようだ。普段、刑務所での生活になんの不満もないような口ぶりだが、やはり人並みにストレスを抱えているのだろう。それよりも俺は…セディのことよりも自分の身を案じる必要があった。
前回の《あの件》のことでエドは数週間の停職処分を受け、俺もボスに苦言を呈された。二度目はない。二度目があれば、エドは降格処分…俺は仕事を失うだろう。セディもそれが何を意味するのか、さすがに分かっている筈だ。
「次、俺を欺いてみろ…お前はひとりで死ぬことになるぞ」
「まるで僕の死刑執行に付き合う気があったような事を言うんだね」
まるで、なんて言葉を用いてはいるが、そうでしょと言わんばかりだ。
俺も前回の釈放後に考えた。この男の死刑執行を見届けるか否かを。俺の人生を狂わせた人間の一人だ。それでもこうして顔を突き合わせている。
これは刑事にしか分からない感覚だろうが、犯罪者と刑事の間には、ある種の絆が生まれるものだ。それが長い年月をかければかける程、奇妙な形で育っていき、蔦のように絡みつく。ひとつの『事件』という共通点を通して、誰よりも深く解りあった気になる。時には家族以上に。それだけ犯罪者と同じように刑事も孤独ということだ。
ここまで考えたあとに、俺は自分がもう刑事ではない事をようやく思い出した。
「死刑執行に付き合う気か
それは、今もある」
俺はフォルダーの中にある事件記録の複製をセディへと渡した。そして帰り支度をする。その間、セディは俺を見なかった。それは俺が嘘をついたからか。それともこの言葉を信じたからなのか。理由なんてものは分からなかったが、初めてセディが俺を見なかった。
その後、刑務官へ連絡を入れるとセディは独房へと戻って行った
最後まで俺を見ることなく、視線は資料にだけ注がれていた。
その意味を考える。これもあの男の作戦であれば功を奏したと思う一方で、何故俺を見ないのかと問い質したい衝動に駆られた。理解が出来ないから苛立つのか。それとも――――――気にしないことにした。
◇
期限は三日間。ボストンバッグに入れたのは、三日分の下着と靴下。あとはノートにペン、それだけだ。念の為、シャツの替えも入れておくか。三日くらい着替えなくても平気で過ごせてしまう刑事の悪い癖がすっかりと染み付いていた。エリカが居た頃は…そこまで考えてやめた。それに今は無駄な事に頭を使うような余裕はない。俺が今日気を配らなければいけないことは二つあった。
一つは今から合流するセディのこと。エドも警護につくが、あのエドだ。安心することはできない。俺からすれば、セディとエドの二人の面倒を見るようなもので、気が休まらない。だが、それはどうにするとして、もう一つ…俺の飛行機恐怖症については、そう簡単な話ではなかった。冷静さを欠くんじゃないだろうか。パニック発作を起こさないとも言い切れない。何故なら人生で一度しか乗った事がないからだ。その時にひどい乱気流に巻き込まれ、生きた心地がしなかった。そのまま墜落するんじゃないかと思う程の揺れを経験して以来、俺は飛行機恐怖症だ。新婚旅行ですら車を使ったくらいの筋金入りで…今思うと、あの頃からエリカとは溝があったように思う。『ハワイが良かったのに』と何度言われただろうか。
「マズい、そろそろ時間だ」
俺は古いニホン車に乗り込むと、トライモントにある空港へと向かった。
空港へ着くと随分と不安げな顔のエドが俺を出迎えた。
「カサイさん! こっちです! 走って」
そう言われても足が重い。随分と多くの刑務官がエドの隣の男を囲んでいるが、中心にいるのは間違いなくセディだろう。これほど多くの刑務官がつくなら安心だ。
「俺は行かなくてもいいだろう」
ジョークじゃない。本気だ。この言葉にエドはかけている眼鏡を指で押し上げると、小さく頭を左右に振った。
「予算がないので搭乗はしないんですよ」
「全員は無理でも、一人くらいどうにかならんのか」
さすがに刑務官一人を雇うカネよりも、自分への報酬が少ないとは考えたくはない。
「君って案外ワガママなんだね」
喧騒の中、飛び込んできたのはセディの声だった。
あの日以降、気にしないと忘れたふりをしていたが、古いシミが再び姿を現すように考えが湧き上がる。それはセディの顔を半分ほど隠すフードパーカーのせいか…それともかけている大げさなサングラスのせいなのか。俺を見ないセディについて嫌でも考えさせられた。
「…エド、携帯してるんだろうな?」
セディから視線を外すとエドに銃の携帯を確認した。前回の自動車での移動とは違い、今回は他にも乗客が居る。万が一があればセディを撃ち殺すこともあるだろう。万が一があればだが。
エドはジャケットを軽くめくると、腰のホルスターをこちらへ見せた。と同時に警官バッジも目に入る。半年ほど前まで俺の腰にもついていたものだ。懐かしいと思うほどまだそう時間は経っていないが、それでも見慣れたものとは言い難くなっていた。
「一般の搭乗よりも先になるので、もう行きますよ」
エドの呼びかけでセディから離れていく刑務官。それと入れ替るように俺とエドはセディの脇に立ち、腰のベルトを掴んだ。一人の刑務官がガムをクチャクチャと噛んで俺のことをじっと見ている。だが、それを不快だと思わずに済んだのは、セディがサングラス越しに俺を見ていたからだ。黒く光を通さないレンズでは、あの湿っぽく陰鬱な目を覗く事はできないが、セディは間違いなく俺を見ていた。
「寂しかった?」
俺は何も答えなかった。仕事中だからと言うわけじゃない。セディの態度に腹が立っていた。俺を無視し、優位に振る舞ったことや俺を支配できると思い上がっていることに対してだ。いつだってこの男のせいで感情が掻き乱され、自分の嫌な顔が引きずり出される。今も腹を立てている自分に苛立ちを覚えていた。
「カサイさん、行きますよ」
エドと俺の二人でセディを挟んで歩いた。手錠はない。それどころか拘束具は一切つけていない。死刑囚でありながら、自由を得たと言ってもいいだろう。なぜセディにだけ自由が与えられるのか。失ってばかりの俺は依然囚われたままだ。塀の外を自由に歩ける身でありながら、この半年間ずっと見えない壁に取り囲まれている。窮屈で息苦しい。この隣の男が死ねば解放されるのだろうか。セディが死ねば――――――だが、これも俺は気にしないことにした。
エコノミークラスの一番後ろの三人がけの席。俺たちはそこへ押し込められるように座った。一応、窓なんてものがはめ込まれているが、この開きもしない小窓など気休めにもならないだろう。俺は客室乗務員に水をもらうと、一気にそれを飲み干した。エドもセディも何か言いたそうにこちらを見ていたが、誰も何も言わなかった。こういった囚人の移送時には、私語は厳禁だ。それも一般客が搭乗し、騒がしくなる頃には破られていたのだが。
「会話は無しなの? あんまり厳しい事を言われるとやる気が出ないよ。それに僕の目から見た事件について、今のうちに話しておきたいんだけど」
俺はエドを見た。エドも俺を見ていた。互いにどうするかと目で合図を送り合ってはいるが、俺はエドのことを何も知らない。目だけで何を考えているかなど、分かるわけがない。
「悪い。何を言いたいのか分からない」
「あぁ、良かった…自分も全然分からなかったもので。喋って良いんですよね?」
互いにフゥと息をつくと声を潜めて喋った。
「いいか、セディ。デカい声を出せばエドがお前を撃つ。他の人間に危害を加えようとすれば、エドがお前を撃つ。俺に触ろうとすればエドがお前を撃つ。もし妙な真似をしたら…」
「エドが僕を撃つ。分かってる。彼には殺されたくない」
しかめっ面のエドが俺を見ており、今度はその目を見るだけで何を言いたいのかよく分かった。
「よし、それなら話せ」
俺がそう言って自分のペースを作り、主導権を握った所で飛行機が動き出した。最悪のタイミングだ。周囲は平然としているが、どう考えてもおかしい。正気じゃない。鉄の塊が空を飛ぶ事に誰も疑問を抱かない事などあり得るのか?
「どうしたの? 酷い汗だね」
「うるさい 黙ってろ」
エンジン音が体に響いてくる。じき離陸するだろう。額に脂汗が滲む。手のひらにも嫌なべとつきを感じて不快だ。あと約6時間は空の上で死刑囚と一緒だ。何もないと言い切れるか? だが、俺にはただ祈る事しか出来ない。
「手を握っててあげようか?」
「ふざけるな」
座席の肘掛けに手を置き、必死にしがみつく。その手にセディが左手を重ねた。口はまだどうにか回るが、払いのける気力はない。
「やめろ」
「エドに撃ち殺させる?」
セディのその言葉にエドが俺を見た。
「カサイさん、自分は発砲なんてしないですから」
「それくらい分かってる!」
苛立つ。まとわりつく不快感と隣の死刑囚のせいだ。ここぞとばかりに俺の手を撫で回し、愉しんでいる。
「君を僕の監視役につけた事は司法省のミスだ。チェックリストに飛行機嫌いの項目はなかったの?」
「あぁ、そうだ 司法省のミスだ。チェックリストにその項目があれば、お前とクソみたいな旅行をする必要もなかったんだ」
その言葉にセディは手を離すと、サングラスを僅かにずらして俺を見た。白銀色に見える青い瞳。それがレンズ越しではなく、直接俺を映した。ただそれだけで胸を締め付けていた窮屈さや息苦しさ、頭の痛みまでもが解消された気がした。そこへ遅れて、苦味を伴った不快感がのしかかる。セディは理解していた。俺が何を求めているのかと言うことや、何に苛立っているのかを。俺をうまくコントロールできて、さぞ満足だろうな。その顔はニンマリと笑っていた。
「君はそうでなくちゃ」
これは最後に面会をした日の答えだろう。
『死刑執行に付き合う気か
それは、今もある』
嘘をついた俺をセディは罰した。厳密に言えば、この瞬間まで罰していた。俺を見ない事で罰を与え、俺を見る事で罪を赦した。セディにとって俺の嘘は、何ものにも代え難い罪なんだろう。雨の夜のこともそうだったように。
気づけば、ベルト着用サインも消えていて、飛行も安定したようだ。セディはエドに事件記録の複製用紙を取り出させると、書き込んでいるメモを自分で読み上げた。
「今回は東海岸のカロスリカーで起きた事件だ。切断された遺体が三体見つかった連続殺人事件。二体は同一犯によるもので、もう一体は…別の犯人による犯行だと思うんだ」
■カロスリカー・チェーンソー連続殺人事件
・三体の遺体
・被害者は10代後半~20代前半の男性
・チェーンソーで解体後、ゴミ袋に入れられ遺棄
それぞれ発見された場所は違ったが、類似点が多い。そこから現地警察は三件の連続殺人事件だとして、捜査にあたっている…というのがこの事件の概要だ。だが、セディは別の犯人による犯行だと見立てた。恐ろしい話だ。チェンソーを使い、遺体を切断するような犯罪者が近距離に二人も存在するとしたら――――――その地域には必ず三人目もいるだろう。
「根拠を話せ」
セディは嬉しそうに両手を擦り合わせると、事件記録の一部を指差して答えた。
「まず二体の遺体には首から上がない。それなのに残りの一体は、切断した頭部もゴミ袋に入ったままだった」
まだ頭部が見つかっていないだけだと言う可能性もある。それでも確かに妙な引っ掛かりを覚える。一体目を捨てたあとに犯人が学習したとして、頭部だけを別の方法で処分するとは考えられない。被害者の特定を困難にさせる為なら、他の部分も同じ方法で処分するだろう。
「頭部が重要なのか? 執着する理由はなんだ?」
この問にセディは声を潜めて言った。
「犯人にとって頭部はトロフィーなんだよ」
声を潜めて言ったところを見ると、いかにその行為が常軌を逸したものであるのかは理解しているようだ。セディも殺害した被害者の小指を集めていた。それはどう説明するのだろうか。いや、今はそんな話を聞きたくもないが。
「お前の言うように別の犯人による犯行なら、それぞれ殺人の理由が違ってくるのか」
最近、刑事時代には湧いてこなかった発想が浮かび上がる。殺人の理由などを考えて捜査した事などなかった。それを《ずさん》という言葉で片付けられると良い気はしないが…捜査なんてものは証拠品を洗い直し、粘り強く聞き込みを繰り返す方法しか知らなかった。先輩刑事から教え込まれたこの捜査方法もそろそろサビがつき始めているんだろう。
「カサイさん、どういうことですか?」
案の定、刑事であるエドには理解が出来なかったようだ。
「頭部が入っていた方は持ち運ぶ為に切断されているが、頭部のなかった遺体は…」
俺はそこで一呼吸置いた。一瞬、飛行機が揺れたせいもあるが、他の客の耳を気にしたからだ。
「切断が目的だったからだ」
エドはまだ理解できていないのか、口を開けて俺をじっと見ていた。
「わからないのか? 切断することで快楽を得ているんだろうって話だ。頭を使ってナニでもやってるんだろう」
わかりやすく顔を歪めたエドは、人差し指を立ててこう続けた。
「つまり、加害者はまだ頭部を持っている…と言うことですよね?」
「捨ててなければな」
「いや、食べてなければね」
セディの言葉には俺も顔をしかめた。想像もしたくない出来事はこの世に数多くあるが…たとえば自分の妻が相棒と子作りをしていただとか、人間が人間を食すなんてことだ。再び嫌な汗が滲んできた。
「だけど、連続殺人事件には変わりないよ。二体は同一犯なんだから、こっちを重点的に捜査した方が良い。おそらく頭部が見つかった方は、大した事件じゃないから」
大した事件じゃない殺人などない。それだけは断言できる。この男の道徳感覚や倫理観はどうなっているのか。女性を30人以上殺害した死刑囚にそんなものを期待する方がどうかしているのは分かっている。それでも正常性を求めるのは、俺が普通の人間だからだろうか。関わる相手が同じような普通の人間であることを俺はいつだって望んでしまう。何度失望した事か分からないが。
「それとまだ聞いて欲しい話があるんだ。頭部をいくつも手元に置いておくなんて、匂いもひどいし、自宅じゃ無理だ」
「大量の石灰を購入している可能性がありますね。あとは住居とは別の不動産を所有している可能性…と」
セディの話を聞きながら、エドはしきりにメモを取っていた。前回はどこか頼りなく、出世するタイプの刑事には見えなかったが、もしかすると化けるかもしれない。俺はエドの評価を見直した。
「現場に行って直接見てみないと分からない部分も多いけど、確実なことは犯人はゲイだと言うこと。それと……」
「それじゃあ、ゲイコミュニティへの聞き込みが必要っと…あとは、20代後半から30代前半の大人しい男が犯人像」
エドがセディの言葉を遮った。その時は気にしていなかったが、あとから思えばこのエドの行動が引き金だったのだろう。それと俺の余計な一言だ。
「エド、何故そう思った?」
俺はエドの学習能力の高さと応用力の高さに少々感動していた。優秀な刑事が生まれる瞬間の目撃者になるかもしれないからだ。エドは走らせていたペンを一旦止めると、考えながら話した。
「まず被害者が若いと言う点で、体力がなければ犯行に及べませんよね。それなら容疑者も若い。だとすると金銭で被害者を誘ったとは考えにくい。じゃあ、何で誘ったのか…それが年齢や顔立ちや振る舞いだとしたら、まぁ、暴力的には見えない筈ですよね。そして衝動を抑えられるだけの忍耐力があり、かつ体力があるのは20代後半から30代前半の男かと…」
ここまでの考えに至るだけで、自分の若い頃とは違う。何か得体のしれない可能性を感じた。
「俺はあまり褒める人間じゃないが…エド、素晴らしいな」
存在を認めて欲しい人間が、その存在意義を奪われたらどうなるのか。ましてやそれが理性を極限まですり減らした死刑囚ならどうなるのか。俺は分かっていなかった。隣の男を普通の人間だと思おうとした俺の落ち度だ。
「……くたばれ」
突然セディがエドの顔に唾を吐きかけた。あまりにも突然のことでエドも俺も一瞬固まったが、次の瞬間にはエドがセディの片腕を捻り上げていた。
「スウィーニー! お前! あぁ! クソっ!」
かけている眼鏡のレンズが汚れていたが、エドはそれを拭う前にセディの手に手錠をかけて拘束した。
「俺が見てる 洗ってこい」
エドはフゥと息を吐き、上着の襟を正すとそのままトイレへと向かった。怒っているが殴らなかった所を見ると、ボスの教育が行き届いているのだろう。先輩刑事は誰だろうか。俺なら間違いなくこの顔面に拳を打ち込んでいただろう。
「あ? 何が気に入らない?」
「君はフィッシャー刑事と呼ばないけど、どうして?」
面会室でエドから電話を受けた時の事を思い出した。あの時、セディは俺に何かを尋ねていた。唇の動きを思い出すとそれは――――
『エドって誰?』
「僕は君と現場に向かう事を条件にしたのに。殺したいよ」
簡単に殺したいと言うが、この男の口から出るとジョークには聞こえない。
「黙れ」
「殺したいよ」
セディが二回目の殺害願望を口にした所で、エドが座席へと戻ってきた。その表情は明らかに怒っていたが、黙って何も言わなかった。空気は全くもって良くない。窓が開くなら開けて入れ替えたいくらいだ。
「航空会社の規約で乗客の拘束は安全上認めないって、そう書いてあった。これは不当な拘束だろ! 今すぐに拘束を解けよ!」
セディが喚き始めた。そのせいで乗客の視線がいくつかこちらへと向いた。死刑囚だとバレたら厄介だ。乗客がパニックを起こすかもしれない。俺の役割はただひとつ。この男の手綱を握り、真っ直ぐに走らせること。捜査にだけ集中させて、こんなふうに権利を主張し始めたら、ぶん殴ってでも止めること。
「セディ、ちょっとこっちへ来い」
俺は無理やりセディの腰のベルトを掴んで立たせた。エドは不安げな顔でこちらを見上げ、ついて来ようとしたが今は逆効果だと俺は首を横へ振った。
「なに? どうしたの?」
「少し楽しもう」
俺はトイレまでセディを引きずって行き押し込むと、そのまま壁に叩きつけた。セディは声一つ出さず、ズレたサングラスの向こうからこちらを黙って見つめていた。痛みや暴力には慣れているんだろう。これでは効果がない。セディの被っているフードをめくって根本が暗いブロンドヘアを右手で鷲掴むと、そのまま便器へ近づけた。
「今のは間違いだ。お前も顔を洗った方がいいんじゃないか?」
「待って。分かった。痛いのはいいけど、汚いのはやめて」
セディの顔を自分の顔の高さまで持ってくると、俺は目を覗きんだ。
「不貞腐れるな。感情は出すな。言われた事だけやってろ。それから、何でも自分が一番だと思うな」
しかし、セディは子供のように頭を振って駄々をこねた。
「嫌だよ! 君にとっての一番は僕じゃなきゃ嫌だよ!」
一番だ二番だと、何かに順序をつけたことはない。誰でもいつだって手前が一番だろう。それでも一つだけ、はっきりとしている事がある。
「お前は一番だ。俺が殺したいリストの一番上にお前がいる。それだけは変わらない、何があってもだ。だから安心しろ」
するとセディは俺の肩に顔を埋めた。ずっしりと重い。まるでそれは全ての信頼を寄せるような、そう言った類の身の預け方だった。もちろん俺は許可していない。今も突き飛ばし、壁にその頭を押し付けることは簡単だ。それでも俺はトイレが狭いと言う理由をつけて―――――気にしないことにした。
「よかった よかったよ…本当に……」
甘えるようにそう口にしたセディに俺は、必要とされる人間の心地よさを感じた。それを感じれば感じるほど体の中が腐っていくような、言いしれない恐怖が絡みつく。そして誰に請うわけでもないが心で繰り返した。これは許されるのかと。それは世間に対する言葉なのか、神に対するものなのか、それとも自分自身へのものか。俺は一体誰に許されたいのか。それを知る前にセディの頭の重みが、不快感へと変換された。
「お客様、どうかされましたか?」
そこでようやくセディを突き放し、腰のベルトを引っ掴んだ。
「今、出る所だ」
ドアを開けるとギョッとした顔の客室乗務員が居たが、俺たちはそんな視線を気にすることなく座席へと戻った。
【SIDE:01 END】2019/12/12 更新